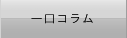|
|
|
|
| こちらのコラムでは週替わりで先生方が順番にお話しをしてまいります。 |
| |
 |
第610回 一口コラム
今回の担当は
施術部部長 小杉英紀です。
令和4年3月2日 |
| |
「”揺らぎ”」
「何かを身に付けるためには反復(練習)が大切」
というのは昔から言われていますしこの方法で上手になったという方もたくさんいらっしゃると思います。同じ意味合いで「継続は力なり」という諺もあります。
ですが、
「反復には意味が無い」
というトレーニング理論があります。
「ディファレンシャル・ラーニング」というもので、ドイツ・マインツ大学のボルフカング・ショルホーン教授が提唱するもので、トレーニングの目的を従来の「適応をするため」に行うのではなく、「異なった刺激を絶えず受けて適応を継続させる」というものです。
具体例を挙げると、赤ん坊はが躓いたり転んだりしながらいつの間にか歩るけるようになるのは、上手くいかなかったことと上手くいったことの「違い」を基にしています。
これは、一見「反復」にも思えますが、この「違い(=トレーニングの変動性、”揺らぎ”とも表現されるもの)」の増幅で自分自身の身体というシステムの構造や秩序を強化していくことを前提としている、とのことです。
つまり、この”揺らぎ”を常に感じることが、個体差のある身体の動かし方の原理原則を強化する、というのです。
物凄く噛み砕いていうと
「慣れたら飽きる(適応の限界は3回まで)から効果が見込めない」
ので同じことを繰り返すや型に嵌め込むのは意味が無いというものです。
例えばゴルフにおける苦手なクラブの克服のためにそのクラブで繰り返し練習をするのはあまり意味がない、というものでしょうか。
ルーティンや練習として同じことの繰り返しをしていたとしても、私たちの身体の状態は歪みや疲労、また気持ちにも左右されながら刻一刻と変化をしています。
その変化にも絶えず適応しているので、厳密にいえば反復ではない(完全に動作は一致しない)のです。
(状況の変化も加えると、平らなマットの練習場で7番アイアンの練習をしても、芝生の斜面になったら練習場と同じスウィングでは狙ったところには打てないですね)
同じことを繰り返しているような動作でも、身体の状態を観察することによってそこにある”揺らぎ”を感じながら行なうこと、目的のために身体が適応出来るようにすることに意味があるのかなと思います。
コロナ禍で在宅勤務になり動くこと自体が少なくなった方も多いと思います。些細な動きにも表れる違いを見つけるのも健康作りの基本的なアプローチなのではないでしょうか。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
2012年 | 2011年 | 2010年以前
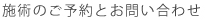
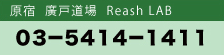
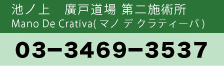
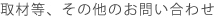 
廣戸聡一の『レッシュ理論』については
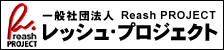
『4スタンス理論』については
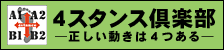
|